平成25年10月18日
民間投資活性化等のための税制改正大綱(事業再編を促進するための税制措置)の解説
今月1日に自由民主党・公明党の政府与党から「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が公表され、また今月15日には、この税制改正と密接に関係する「産業競争力強化法案」が閣議決定され今臨時国会に提出されました。
税制改正大綱は、年度末の税制改正に向けて年末に決定されるのが通例ですが、消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要との観点から民間投資を活性化させるための税制措置については、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定することとされました(民間投資活性化等のための税制改正大綱1頁)。
産業競争力強化法案では、企業に眠る優れた事業・技術・人材等の経営資源を切り出し、又は統合してシナジーを実現するなど、企業組織再編を支援する措置を講ずることとされており[1]、これに合せて税制改正大綱には下記(1)の特例措置が盛り込まれています(民間投資活性化等のための税制改正大綱12頁)[2]。
(1) 事業再編[3]を促進するための税制措置
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日までの間に同法に規定する特定事業再編計画[4]について認定を受けたものが、積立期間[5]内の日を含む各事業年度のその積立期間内において、その特定事業再編計画に記載された同法に規定する特定事業再編[6]に係る同法に規定する特定会社[7]の特定株式等[8]の取得(その特定事業再編前の取得を除きます。)をし、かつ、その特定株式等をその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(その特定事業再編をした最初の事業年度において、その特定事業再編前からその最初の事業年度終了の日まで引き続き有しているその特定会社の特定株式等の帳簿価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含みます。)は、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとされます。
この準備金は、その積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間で、その積立期間終了の日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入することとされます。
なお、この措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されますが、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に特定株式等の取得をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度においてその準備金積立相当額の損金算入ができることとされます。
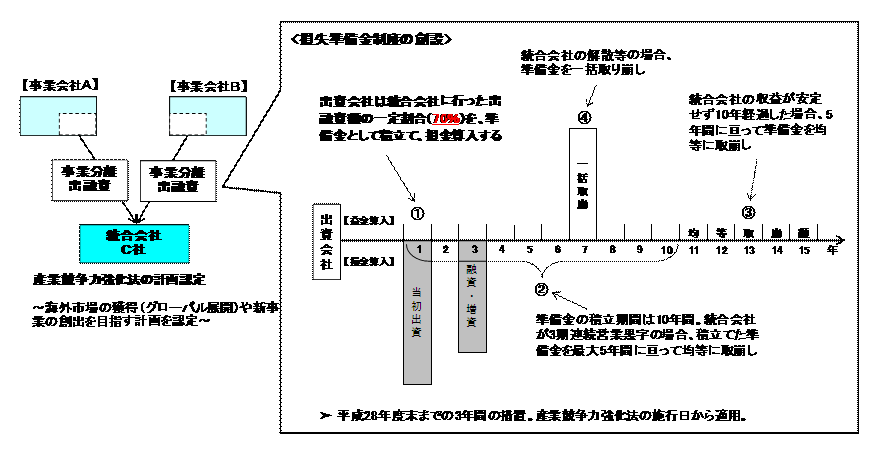
(経済産業省資料より)
(2) 産業競争力強化法案における用語の意義
① 事業再編
事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次のⅰ及びⅱのいずれにも該当するものをいいます(産業競争力強化法案2⑪)。
ⅰ 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(その事業者の関係事業者[9]及び外国関係法人[10]が行う事業の構造の変更を含みます。)を行うものであること。
(ⅰ) 合併
(ⅱ) 会社の分割
(ⅲ) 株式交換
(ⅳ) 株式移転
(ⅴ) 事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含みます。)
(ⅵ) 出資の受入れ
(ⅶ) 他の会社の株式又は持分の取得(その取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限ります。)
(ⅷ) 関係事業者の株式又は持分の譲渡(その譲渡によりその事業者の関係事業者でなくなる場合に限ります。)
(ⅸ) 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(その取得によりその外国法人が外国関係法人となる場合に限ります。)
(ⅹ) 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(その譲渡によりその事業者の外国関係法人でなくなる場合に限ります。)
(ⅹⅰ) 会社又は外国法人の設立又は清算
(ⅹⅱ) 有限責任事業組合に対する出資
(ⅹⅲ) 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
ⅱ 事業者がその経営資源[11]を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
(ⅰ) 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供(「新商品の開発等」といいます。)により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
(ⅱ) 商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
(ⅲ) 商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
(ⅳ) 新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
② 特定事業再編
事業再編のうち、2以上の事業者が、それぞれの経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用して、2以上の事業者のそれぞれの事業の全部又は一部の生産性を著しく向上させることを目指したものであって、次のⅰ及びⅱのいずれにも該当するものをいいます(産業競争力強化法案2⑫)。
ⅰ 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行うものであること。
(ⅰ) 2以上の事業者のそれぞれの完全子会社(一の事業者がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社をいいます。)相互間の新設合併又は吸収合併
(ⅱ) 2以上の事業者が共同して行う新設分割
(ⅲ) 2以上の事業者のいずれか一の事業者の完全子会社に、その2以上の事業者のうち他の事業者が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる吸収分割
(ⅳ) 2以上の事業者のいずれか一の事業者の完全子会社が行うその2以上の事業者のうち他の事業者からの出資の受入れ
(ⅴ) 2以上の事業者が共同して行うそのそれぞれの完全子会社の発行済株式の全部を取得する会社の設立
ⅱ 次に掲げる会社(「特定会社」といいます。)のいずれかが、外国における新たな需要を相当程度開拓し、又は新商品の開発等により国内における新たな需要を相当程度開拓するものであること。
(ⅰ) ⅰ(ⅰ)の新設合併により設立された会社又はⅰ(ⅰ)の吸収合併後存続する会社
(ⅱ) ⅰ(ⅱ)の新設分割により設立された会社
(ⅲ) ⅰ(ⅲ)の吸収分割により事業に関して権利義務の全部又は一部を承継した会社
(ⅳ) ⅰ(ⅳ)の出資の受入れをした会社
(ⅴ) ⅰ(ⅴ)の会社の設立により設立された会社
③ 特定事業再編計画
2以上の事業者が実施しようとする特定事業再編に関する計画をいい、2以上の事業者は、特定事業再編計画を作成し、主務省令で定めるところにより、これを集中実施期間[12]中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができます(産業競争力強化法案26①)。
なお、特定事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならないこととされています(産業競争力強化法案26②)。
ⅰ 特定事業再編の目標
ⅱ 特定事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
ⅲ 特定事業再編の内容及び実施時期
ⅳ 特定事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
ⅴ 特定事業再編に伴う労務に関する事項